九州テレコム振興センター(KIAI)は内閣府認可の非営利型一般社団法人です
TEL. 096-322-0120
〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町4番20号
会員向けWebマガジンKey-Eye
Key-Eyeとは?
これからの九州の情報化推進に向け、ひとつの
「鍵(Key)」となる、あるいは新たな「視点(Eye)」
となる話題を提供していこうとする思いを込め、
「Key-Eye」というネーミングにさせていただきました。
◆Key-Eyeあるメッセージ
(ICT分野有識者による
全4回のコラムを掲載)

【2025年度執筆者】
北陸先端科学技術大学院大学 副学長・教授
丹 康雄 氏
2025年度「Key-Eyeあるメッセージ」は丹様よりいただくこととなりました。ご自身のこれまでの活動等を振り返り、ICTのこれまでの変遷とその将来に関するコラムを年間を通じていただきます。最終回となる第四回は「ビッグデータからAI0へ」をテーマとして寄稿いただきました
◆Key-Eyeあるトピックス
(全国各地の様々なICT分野の
トピックスを掲載)

一般社団法人Tannbo
代表理事 小野寺 直喜 氏
現在の農地施策における「農地集約」という大きな課題に対し、アルゴリズムとデータに基づく効率・効果的な解決策の提示を可能とするシステムを展開しておられる(一社)Tannboの取組みについてご紹介していただきました。
◆Key-Eyeある人
(ICT分野で活躍されている産学官
関係者の熱い思いを掲載)

「岡安 崇史 氏」
九州大学 大学院農学研究院 環境農学部門 教授
「データ駆動型農業」の実現を通じ、農作業の効率化・省力化、高品質な農作物の安定生産に向けた取り組みを進めておられる岡安氏より、当該研究開発に関する寄稿をいただきました。

「豊福 鮎美 氏」
MamaLeaf株式会社 代表取締役
ご自身の育児体験を通じて感じた育児の非効率性に関し、IT活用を通じ「テクノロジーを身近にし、頑張らない子育て環境」づくりに向けた取り組みを進めておられる豊福様より、MamaLeaf(株)における事業展開等について寄稿いただきました。
◆Key-Eyeあるまちづくり
(九州でのICTを活用した様々な
地域づくりをご紹介)
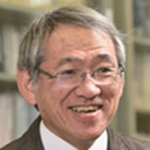
「CDLE福岡」
CDLE福岡リーダー
第一薬科大学薬学部教授(株式会社ファーマAIラボCEO)
有馬 英俊 氏
AIデバイドを少しでも解消すべく、AIに関心を持つ人々が分野や立場を越えて集い、学び合う場を提供しておられるCDLE福岡様より、様々なコミュニティ活動の取組みについて寄稿いただきました。
【編集後記】
先日、日経新聞の記事に、AIのスキルに哲学のスキルも併せもつ人が増加している、という記事がありました。記事は主にAIが下す判断に対する倫理的アプローチの重要性という、どちらかといえば今後のAI開発に関する観点からの内容でしたが、昨今の生成AIが拡充する時代において、この哲学というものは、生成AIを使いこなす側においても非常に重要な要因になってきているのでは、と個人的には思うところです。
一般的に哲学というと、難解な思想史や抽象的な議論を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし哲学の本質は、思考の内容の違いを競うことではなく、なぜそのように考えるのか、どこからその考えが立ち上がってきているのか、という、つまり思考の相違の起点、あるいは思考の源泉を掘り下げていく営みにあるのではないでしょうか。私は、哲学とは「正解を提示する学問」ではなく、「その正解に至る評価軸そのものを探求する学問」でもあるのだろうと考えています。この発想こそが生成AI活用において重要なポイントになってくると思われます。
生成AIは、膨大なデータを基に、もっともらしい「答え」を瞬時に提示してくれます。業務効率化、意思決定支援、文章生成、分析補助など、私たちは日常のあらゆる場面で恩恵を享受しつつあります。しかし、その一方で、生成AIが提示する答えを「良い」「正しい」「使える」と評価する基準とはどうなのでしょうか。例えば、ある業務改善において「処理時間が短縮された」「コストが削減された」という結果が得られたとします。多くの場合、これは成功と評価されます。しかし、その評価軸は本当に十分なのでしょうか。処理時間の短縮は、誰にとっての価値なのか。削減されたコストの先に、どのような社会的意味があるのか。あるいは、効率化の結果として失われたものはなかったのか。こうした問いは、単なる数値指標だけからは見えてきません。
ここで重要になってくるのが、哲学的思考によるアプローチだと思われます。「何を達成したか」を問う前に、「達成された先にあるものとは」、さらには「達成された先にあるものはどう評価されるものなのか」をまずは問う必要があるのではないでしょうか。
「AIに何ができるのか」の議論だけに固執せず、「AIのもたらした結果」に対し私たちは何をもって判断、評価していくのか、これがある意味AI社会における我々人間の本質的問いかけなのかもしれません。
AIは解決策を高速・高度に検討し、その選択肢を整理したうえで、最適解らしきものを提示してくれますが、その最適解らしきものが「妥当である」「望ましい」と判断する根拠は、基本的にAIの内にはありません。その評価をくだすのは、あくまでも私たち人間です。ところが、AIが高度化すればするほど、私たちは無意識のうちに「評価」をAIに委ね始めているのではないでしょうか。AIが示した順位、スコア、推奨案に従うことが合理的であるように見え、その背後にある前提条件や価値観を吟味する機会が減ってきているのではないかと。ここに、AI中心のデジタル社会特有の危うさがある気がします。AIは過去のデータをもとに未来を予測しますが、その「過去」がどのような価値観に基づいて蓄積されてきたのかについては沈黙しています。言い換えれば、AIは評価軸を「事前に設定されている事実」として受け取る存在であり、基本的にはその前提自体を疑うことはないと考えられます。だからこそ、その役割は人間側に残されているのです。
例えば、成功と失敗の構図を描くとした場合、現状を原点(つまり座標軸上の0点)とすると、成功した地点は右端(座標軸上の+位置)、失敗した地点は左端(座標軸上の-位置)に描画することが一般的に多いと思います。これはこれで特に異論はないのですが、ここでこの描画された線を原点をもとにして折り曲げてみるとどうなるでしょうか。そうすると両端にあった成功と失敗とは同じ位置となり、もう片方にあるのは現状、といった、それ以前とは全く異なった新たな2軸が誕生していることがわかります。これはつまり、「何もしなかった」「何かを行った」という評価軸に基づく構図ともいえるでしょう。つまり、評価軸とは決して中立でも絶対でもない、という点です。効率性を重視するのか、公平性を重視するのか、短期的成果を見るのか、長期的影響を見るのか。評価軸の置き方が変われば、同じ結果であっても、その意味は全く異なるものとなります。にもかかわらず、AI中心のデジタル社会では評価軸そのものが「前提条件」として埋没し、そこの議論が置き去りになりがちとなってきていないでしょうか。
みなさんも良くご存じの哲学者ニーチェは、「事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。」という言葉を残しています。これは、私たちが事実と呼んでいるものは、既に何らかの枠組み、すなわち評価軸を通して切り取られた結果にすぎない、という点への自覚を促す言葉ではないかと個人的には解釈しています。もう少し個人的解釈を拡大させると、この言葉は、ものごとに対し常に評価という行為をなす、そのこと自体が私たち人間を定義するひとつの要因ではないか、とも読み取れる気がします。そして、この際の評価軸とは、単なる判断基準というモノサシのような類ではなく、それは、私たちが、価値とは何なのか、その価値に基づくビジョンとは何なのか、あるいはもっと大きく捉えれば、私たちがどのような社会を目指し、後世に向け何を価値あるものとして残していこうとしているのか、そうした思考を映し出すための起点そのものとも言えるのではないでしょうか。評価軸を自覚せずにAIを使い続けていくことは「合理的な判断=前提となる評価軸を疑わない判断」という状態に陥ってしまうことを意味するのかもしれません。
様々な問いかけに対して即答可能な生成AIとの共存に際し、我々人に求められているのは、より速い判断力、ということより、むしろ立ち止まって考える力の方なのではないでしょうか。その判断は、どの評価軸に基づいているのか、その評価軸は、どのような価値を優先しているのか、そしてその選択は、どのような社会、未来につながっていくのか。
哲学的思考とは、このような「評価軸の探求」、といったデジタル社会において人間が唯一有する重要な役割であると思われる行為を大きく支える営みであり、この点に関して私たちはこれまで以上に意識を向けていく必要が高まってきていると感じます。
まずは簡単に、思考の起点を問い直す(もっと簡単にいえば発想の転換)行為から日々取り組んでみても良いかもしれませんね。先日やってしまったその失敗(笑)、果たして本当に失敗なのでしょうか、ひょっとすると・・・。
バナースペース
九州テレコム振興センター
(KIAI)
〒860-0016
熊本県熊本市中央区山崎町66番7号
TEL 096-322-0120
FAX 096-322-0186
